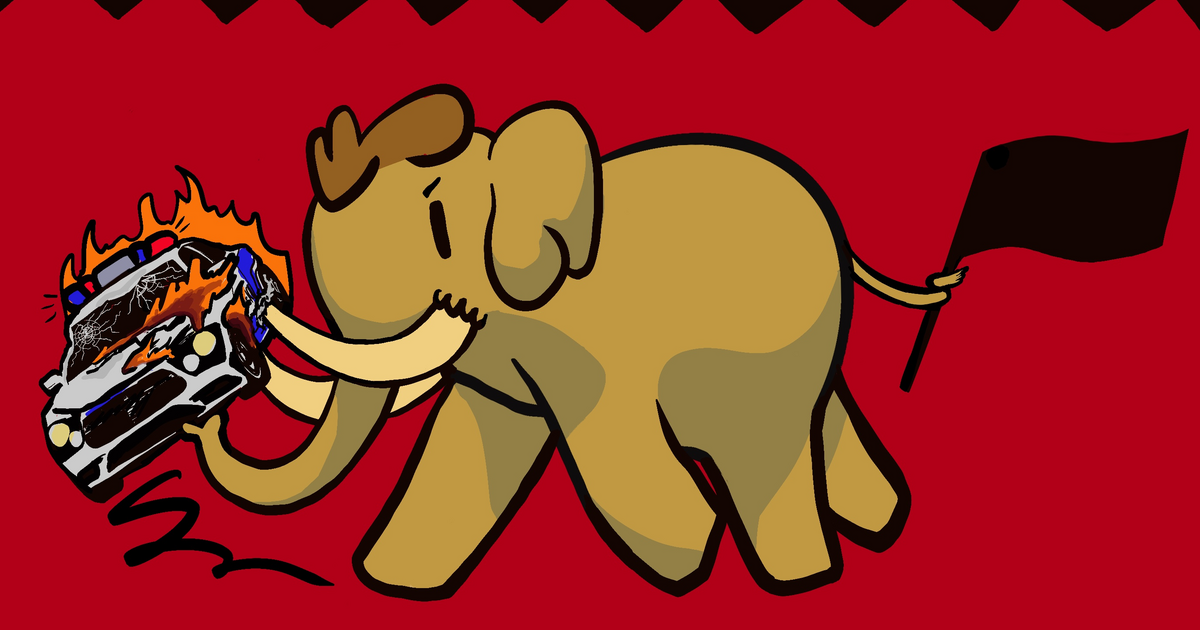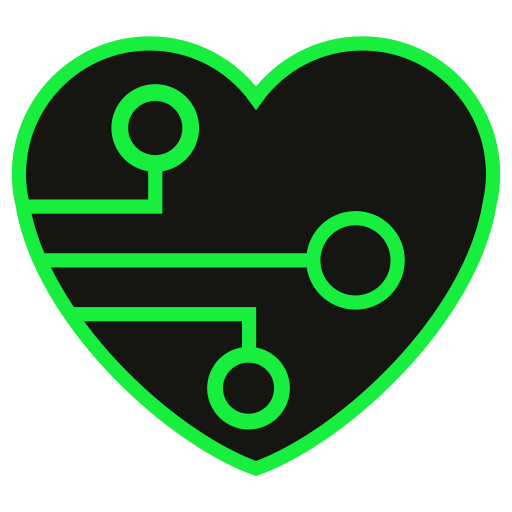『坂本図書』坂本龍一著。
https://honto.jp/netstore/pd-book_32779957.html
坂本龍一が読書に触発されて自分のことばを綴るという短いことばの連続。
斉藤幸平と
マイケル・ハートの対談を読み、
未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か? (集英社新書)
https://honto.jp/netstore/pd-book_29773193.html
“日本では短絡的に選挙、カリスマ的なリーダー、という話になり、選挙以外に政治にコミットできるチャンネルは少ない。
だが、それだけではない。(サンダース現象・社会運動がサンダースを盛り立てている)
また、カリスマは古い。(コモンの例)”
と残しているのが心強かった。
この社会運動によって候補が押し上げられたサンダース現象については
すばりコモンズという出版社から出ている
「ソウルの民主主義」(大内裕和・白石孝対談部分)にもくわしく
https://honto.jp/netstore/pd-book_28905258.html
アメリカ・イギリスはじめ欧米について、右派の台頭が断片的に報道されるが、#反緊縮 運動などはほとんど伝わっていない。
2010年代に入ってから、左派の新しい潮流が明確に見えてきた。
多くの動きがあるなかで最も注目されるのがアメリカのバーニー・サンダース、イギリスのジェレミー・コービンの登場。
いずれも貧困に直面あるいは民主主義の再生を望む、若年層の支持を受けている。
サンダースの躍進を支えた社会運動として
・オキュパイ・ウォール・ストリート
・最低賃金を時給15ドルに引き上げる運動
・生活賃金(リビング・ウェイジ)運動
サンダースの主張であったニューヨーク州の公立大学授業料無償化が実現している。
イギリスも同様に若者のワーキング・プア問題が深刻で、当初泡沫候補扱いされていたコービンが当選。
ほかにスペインのポデモス、ギリシャの急進左派連合などの動きがある。
どんなに見どころのある政党や候補者でも、
やっぱり最終的に特定政党に入れろという圧を感じたら、人が警戒するのは仕方ない。
選挙がゴールのように見られてはダメだし、選挙だけで変えられると信じていない人をどう現実的に動かすかといった時に、政党単位でなくて個人単位でも、自分たちにできること、自分たちにしかできないことをしていくことを、全然卑下しなくていいかなと思う。